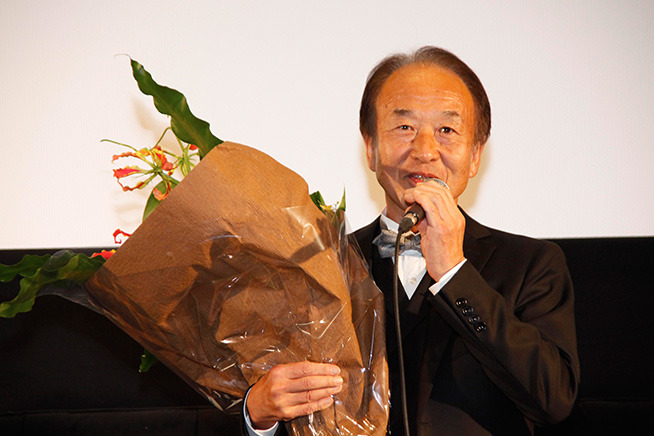10月17日(金)、イオンシネマ京都桂川で、特別上映・京の映画『人間 –Ningen- The Human』が上映され、舞台挨拶に出演者の吉野眞弘さん、李小牧(リー・シャム)さん、鮎川めぐみさん、和島政子さん、プロデューサーの谷元浩之さんが出席しました。

京の映画とは、海外の人から見た日本、そして京都を、京都に根ざしている監督がそれぞれの視点で“京都”を描いた作品を集めたもの。
『人間 –Ningen- The Human』の監督は、カンヌ国際映画祭入選など数々の経験を持つトルコ&フランス出身の男女ペア、チャーラ・ゼンジルジ監督&ギヨーム・ジョヴァネッティ監督。古事記とギリシャ神話が絡み合い、狐と狸の化かし合い劇が繰り広げられるという奇想天外な物語です。映像の美しさと独創的な世界観はもちろん、キャストも実にユニーク。主演を務めた吉野さんは、中小企業の現役経営者! さらに演技経験のない社員やサンバチームなど、監督と主要撮影スタッフ以外、役者を含めてすべて一般の人々によって製作された映画なのです。
2013年のトロント国際映画祭で入選した日本映画のなかでも「一般の人々により製作にして入選」という快挙を成し遂げた、極めて異質な作品として注目を集めました。
主演で狸役を演じた吉野さんは、「冒頭に断りを入れておかなくてはいけないんですが、私の会社でロケをしたんですけど、私の会社は至って健全な会社でございます。今年で21周年ですが、事実上、無借金会社ですのでご心配なく(笑)。設定はあくまで映画の上でのことで、ここを誤解されますと大変なことになりますので…」とことわりを入れ、お客さんから思わず笑いが。さらに「京都国際映画祭の第1回目に参加できて、こんなにうれしいことはございません。そして素晴らしい劇場で上映していただくのは、私だけでなくスタッフも含め、協力していただいた人たちも喜びだと思います」と語りました。
続いて李さん。「“歌舞伎町案内人”の李小牧役(本人役)を演じた李小牧です。日本に来日して26年間で、まさか自分が参加した映画が京都で国際映画祭に参加できるなんて。何週間も前から緊張しました。今も緊張しています」と感激しきり。
鮎川さんは「3年前から京都に住ませていただいてます。足を骨折して『これからどうしようかな』というときにラジオカフェの方を通して吉野さんにお会いし、そして監督にお会いしてこの映画に参加させていただきました。昨日のオープニングセレモニーでは、本当に不思議な体験をして、映画界を作られてきた皆さんの貴重なお話を聞くことができ、感謝の気持ちでいっぱいです」と話しました。
狐役を演じた和島さんは、実生活でも吉野さんの奥さま。「まさか自分が狐だったとは。映画ができあがって初めて見たときに知りました。本当に騙し合いではないんですが、自分がすっかり騙されていました」と明かしました。
吉野さんの会社で働く谷元プロデューサーからも挨拶が。「自分にとってもこの映画は初めての長編作品で、監督は今日、本当にここに一緒に来たかったんですけど、残念ながら今はパリで活動をしていまして、『くれぐれも皆様によろしくお伝えください』と申していました」とご挨拶。
さらに映画の背景についても。「すべては人との出会いによって生まれた映画です。この映画が完成するまでの間、多くの京都の仲間たちに助けられました。それで京都国際映画祭の記念すべき第1回に上演されたというのは、我々にとってとても特別なこと。皆さんに、少し恩返しができたのかなと思っています」と感謝の気持ちを。
監督と主要撮影スタッフ以外、吉野さんを含め役者の皆さんすべて一般の方々の手で製作されたという経緯についても谷元プロデューサーから明かされました。
「もともと、僕らは東京でショートフィルムの映画祭をやっていたんですが、そのときに監督に出会いました。監督は昔から日本という国に憧れており、それに加えて古事記など日本の神話性にも興味があって、2010年にヴィラ九条山というアーティストレジデンスで京都に来ました。そのときに、彼らが自分たちの足で京都中を歩き、伏見稲荷、能舞台を徘徊するうちに人との出会いも増えて、ある日、我々に『京都でこんなインスピレーションをもらったから、こういう物語を作りたいんだけど』と、うちの吉野に連絡が来ました。うちの会社は翻訳をメインにやっているので、映画製作はやったことがなかったんですが、冒険好きの吉野に火が付きまして、そこで会社一同を上げて『この企画を実現させよう』と、現在に至りました」と、監督との出会いから映画製作に至るまでの秘話を明かしました。
さらに、“縁”でキャストが決まったことについての話も。「京都で長年お付き合いさせていただいている中で、和島さん、李さん、鮎川さん、すべての方との出会いが生まれました。監督が、映画を形にする時に人からの紹介でどんどんキャスティングをしていったという経緯もあります。かなり特殊なやりかただと思いますね」とも。
さらに驚きなのが、この映画には台本がなかったということ。谷元プロデューサーは語ります。「演出は、ここにいる4人が一番苦労したと思います。もともと映画の作り方自体が特殊で、演出の方法において、台本を使わず一般人の方が物語をもらい、その物語をベースに映像を作っていく、というのはひとつのスタイルなんですが、監督にとっても挑戦だったと思います。なおかつ、自分たちが日本語を喋らない中で、台本なしで、異文化の中で、出会いだけで物語を作れるのか、という挑戦をしてみた、という部分が大きいのだと思います」と監督の思いを代弁。
実際に映画の中でも吉野さんが「この先のストーリーはどうなるんですか?」と尋ねるシーンがあり、まさしくそのような状況の中、映画が創り上げられていったのが伺えます。
吉野さんは「ストーリーはまったくありませんし、セリフもございません。ただその瞬間だけ、3分ぐらい前に『このストーリーはだいたいこういう形だから、だいたいこういう風になるようにしてくれ』と。指示はそれしかないんです」とも。冒頭の朝礼シーンもまったくの即興だったというから驚きです。「だからこそ、素人の私でも演技ができたのではないかと。固いシナリオがあると、むしろそれにこだわって、『うまくやろう』という思いが入ってしまったかもしれません。『何も怖いものはない』という心境でした」と告白。
台本がないなか、どのようにセリフのやり取りが繰り広げられていたのでしょうか? 李さんは「たとえ26年間日本にいても私は中国人ですし、監督の言葉はトルコ語とフランス語でわかりません。そこで通訳の人を通して日本語で伝えてもらっても、狸と狐の話がまったくわからない。だから、私は勝手に『こう言いたい』と言ったりとか、臨機応変にやるしかない。たどたどしい日本語で全部は伝わらないかもしれないけど、表情や感情でやろう、と。それが楽しかったです」と体当たりで挑んだ様子。
鮎川さんは、実は演劇学科卒業で大竹しのぶさんと同級生なのだとか。「吉野さんと初めてお会いした時に『実は演劇に憧れていたけど、自分は下手だなと思ってあきらめたんです』という話をしていたら、『映画に出ませんか』とお話をいただいて。悩んたこともありました。でも、吉野さんからエネルギーを感じたので、その場に一生懸命いた、という感じです」と撮影時をふり返りました。
和島さんは「セリフが難しくて、何を言っていいのかわからなかったです。こちらから何か言っても吉野は『ああ』とか『うう』としか言わなかったので(笑)、『じゃあどう返していけばいいのかな』と悩みましたね。でも、撮り進めていくうちになんとなく『こういうストーリーなんだろうな』と想像がつき、“そのようになっていった”というか、“普段通り”ですね(笑)。だから、演技というより素をそのまま出したと思うので、ちょっと恥ずかしいです」とニッコリ。
今回、改めてビッグスクリーンで作品を鑑賞した吉野さんは、「人間というのは、一生懸命やって、やってもダメで。結局、自分の生き様、“素”を出すほかないんですね。飾ることではなく、そのままを人間として生きることが大切なんだなということを、今改めて理解しました」としみじみ語りました。
鮎川さんも「映画に出ている皆さんが、人としてちゃんと一生懸命生きてらっしゃる人たちばかり。何度観させてもらっても、そのときどきで引き込まれる、魅力のある映画だと感じました」とふり返っていました。